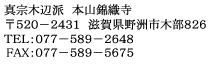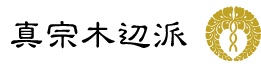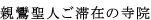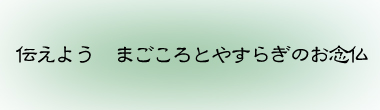HOME![]() 親鸞聖人ゆかりの里
親鸞聖人ゆかりの里![]() 矢射田の蹟
矢射田の蹟

矢射田の蹟 藤塚
宗祖親鸞聖人が、嘉禎元年(西暦1235年)に関東から御帰洛の途中、しばらく木辺の毘沙門堂に御逗留なされ、本願念仏の教化に当っておられました。
あるとき、田植えする農民をご覧になりながら畔に腰を下ろしてご休憩なされ、早乙女たちへ御自らおつくりになった田植え歌をお教えになりました。
みんなは、鍬に菰をかけて、聖人はそこにお掛けいただき、そのお膝もとに集まって習いました。
早乙女たちは、それを習い覚えては田におりていって謡いながら田植えをしました。聖人は、その姿を喜んで眺めておられました。
農民たちは、田植え歌を教えていただいた聖人が凡人ではないと知り、かの聖人ご使用の菰を清らかな川の水に流しました。
すると、それは夜ごとに元の所までさかのぼってきたので、勿体ないことだと思い、焼いて灰にし、土中に埋めました。
その菰を焼いて灰にし埋めた所が「矢射田 の蹟 」と言われ、菰を捨てた川を「菰捨て川」と呼んでいます。
この際お教えくださった歌の節は、上管和讃の一部となり、本山声明の根幹として、今日も毎年の報恩講の際に唱和しております。
また、近在には、聖人がお使いになっていた杖を差しておかれたら 芽が出て藤の木が生えてきたという伝承のある「藤塚」など、いずれも親鸞聖人にまつわる 伝承地として今日に残っております。